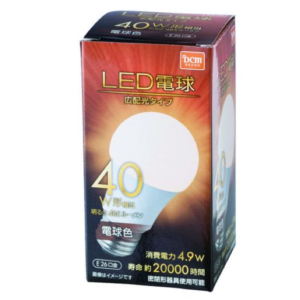2018.10.17 秋の夜長は照明で快適に

本当に秋の日は釣瓶落とし。秋分の日を過ぎると日に日に夜が早まって行く感がありますよね。ところで藪から棒ですが、お部屋の「灯り」や「照明」を、つい「電気」と呼ぶ方って、日本中に、どれくらいおられるのでしょう? よく「電気消して」「電気つけて」「電気つけっぱなしで、もったいない」……って、言いませんか? 私は無意識レベルで言ってしまっています。
つまるところ「灯り」「照明」イコール「電気(によるもの)」なのですよね。エジソンによる白熱電球の長時間点灯の成功から140年ほど経ち、「照明」の主流は「白熱灯」から「蛍光灯」、「LED」へと移り変わって来ています。
「照明」があることによって、私たちは真夜中であってもまるで昼であるかのように暮らしたり、仕事をしたりすることができるようになりました。「照明」の進化により、私たちは人類の歴史の中でもかなり特殊なライフスタイルを実現したのです。
それは例えば夜中に事故や急病があっての緊急手術を可能にした反面、意味もなく起き続けて昼夜逆転してしまうようなライフスタイルをも可能にし、かつてはなかった睡眠の問題などを引き起こしたりしているのです。
ところで、私たちの身近にある、いわゆる「白熱灯(球)」、「蛍光灯(球)」、「LED」。それぞれの違いや定義、ご存知でしたか? ざっくりご説明しましょう。
「白熱球」とは、フィラメント(発光線条)が電流によって発光することを照明に利用したもの。
「蛍光灯」は、フィラメントに高い電圧をかけ発生した紫外線を蛍光物質に当てて出た赤青緑の光を混ぜて白い光に変換したもの。
「LED」とは、発光ダイオード(2つの、電気を通したり通さなかったりする半導体が合わさってできたもの)が電流を流すことで発光したもの。
このように同じ光に見えて作り出されるプロセスからして、だいぶん違いがあります。
その違いは電球(電灯)の寿命にも如実に表れています。「白熱球」は、寿命およそ1000〜2000時間。「蛍光灯」は13000時間程度。「LED」は約40000時間。最短と最長では、なんと40倍もの開きがあります。ちなみに、10000時間は約400日です。
また、かかるコストにも大きな差があります。例えば60Wの「白熱球」を、1日8時間点灯すると、1年で5000円程度の電気代がかかると試算されます。これが「蛍光球」では、約1000円、「LED」では、約500円ほどと、ここでも10倍もの差が生じます。
電球自体のコストに目を移すと、かつては同じ60Wの電球を「白熱球」で買うと300円、「蛍光球」で買うと1000円、「LED」で買うと3000円、と言われるくらい価格差がありました。しかし最近では「LED」でも600円程度と、価格差はなくなってきています。
こうなると、とにかく今すぐにでも全て「LED」にしない手はないような気になってきますね。しかし、実は「白熱球」を使っていた照明器具に「LED」をそのまま挿せばいい、というほど簡単には乗り換えられないのです。
電球の口金のサイズや形状が合致する照明器具間では、「白熱球」を「LED」に差し替えられる「可能性」があります。が、互換性の判断は照明器具メーカーに確かめる必要があります。
「白熱球」に比べ「LED」は重く、複数の電球を取り付けるシャンデリアなどの照明器具では安全性を損なう可能性があります。また、照明器具の構造によっては熱負荷がかかるなど、電球の性能低下や故障につながることがあります。
さらに、照明器具自体の寿命にも考えを及ばせる必要があります。電気製品の一種である照明器具は、概ね10年が安全に使用できる期間と言われています(※1)。特に住まいを新築する際に新しい照明器具を一気に入れたような場合、この10年経過のちの照明器具交換は大きな経済的負担を強いることになり、故意ないしは無自覚的に見過ごされることも少なくありません。
気をつけなければならないのは、「LED」は前述したように寿命が約40000時間もあります。つまり仮に1日に10時間点灯するとして、11年も持つことになります。
場合によっては新品の照明器具に挿しても、電球より前に照明器具が壊れてしまう可能性もある、ということは念頭に置いておいてもいいかもしれません。
照明はただ明るければいい、というフェーズはもう終わりました。近年、照明、その明るさが生理的に及ぼす、心や体の健康への影響力は決して小さなものではないということが少しずつ明らかになってきています。
リビングで必要な光量とはどれくらいか、ダイニングに適した光色とは何色か、勉強をする子供部屋に、ゆっくり休むべき寝室にふさわしい光とは何か。照明をどういうものにするか、その光源を何にするかという問題は、電気代の多寡だけで選びきれるものではないのだと思います。