2018.03.28 スマートなゴミ出しの流儀|ズバッと解決!<季節のお悩み相談室>
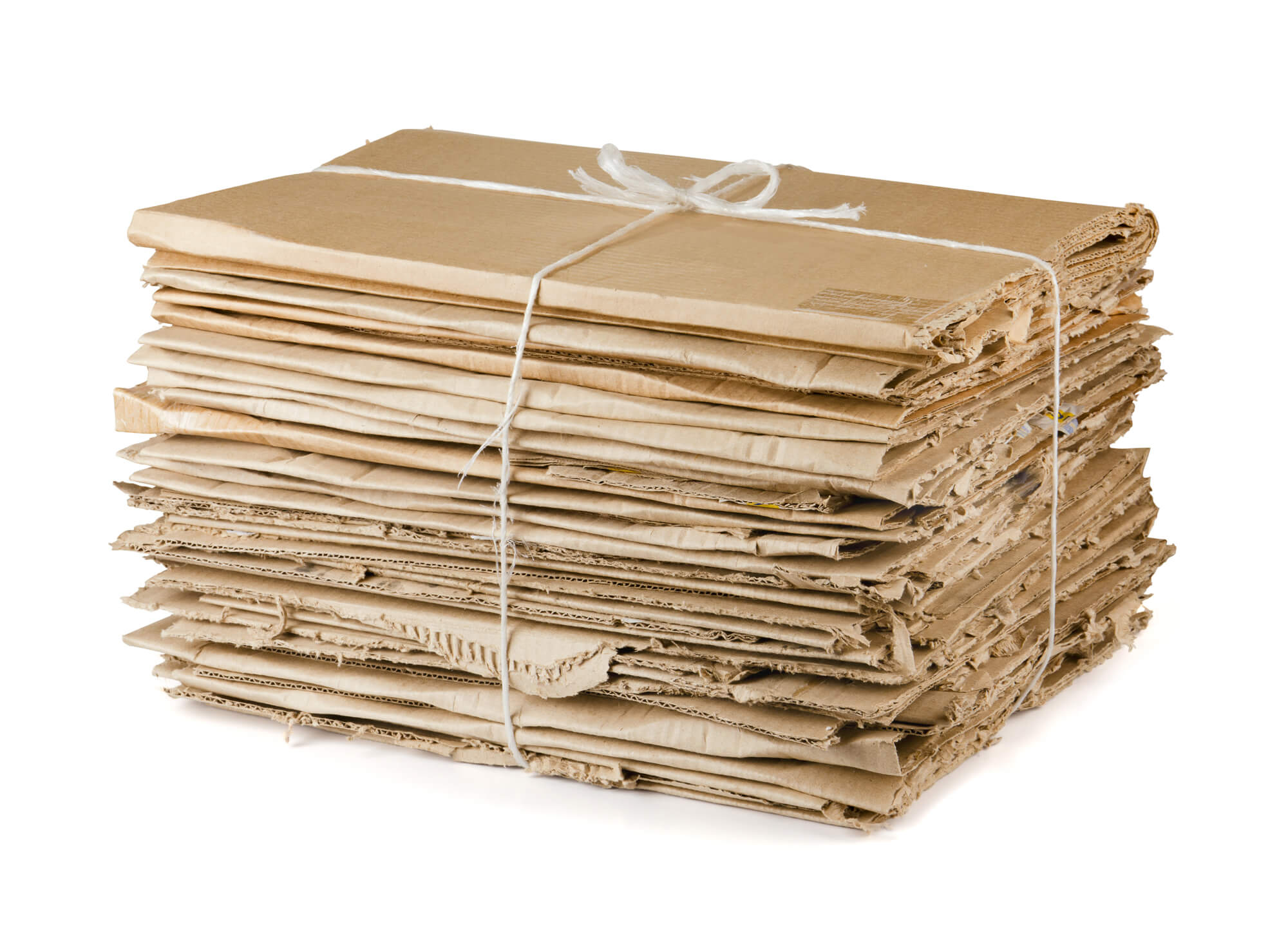
ゴミ収集日の朝。「おはようございます」と行きあう、4人。
Aさん…何はともあれ、いつもゴミ袋がパンパン。会うたびにサンタクロース状態。
Bさん…缶がいつもすごい大量(透けて見えるに第三のビール)。
Cさん…えっ、レジ袋1つぶん?
Aさんは5人家族のパパさん。Bさんはバリキャリのお姉さん。Cさんはエコロジストな奥さん。まあ、いかにもいかにも……なんですが、本当にゴミってその人、ご家庭そのもの。と、その場にいたDさんたる私も我が家のゴミ(なかなか多量!)を後ろ手に隠しながら、思ったわけです。「ちょっと、恥ずかしいかも」と。
ゴミ。自治体によって、分別の流儀には違いがあるのでなかなか一概には言えないのですが、大まかには以下のような分類がなされていることが多いようです。
●もえるゴミ
●もえないゴミ
●かん
●びん
●ペットボトル
●繊維
●古紙類
●食品包装プラスチック
●有害危険ゴミ
●粗大ゴミ
●小型家電等
●収集できないもの
その人、家庭によって日常的に出るゴミの内容というのは、日々そう変化するものではありません。だから「いつもペットボトルがやたら多い」とか「食品系が多い」などといった、ライフスタイルの写し鏡のようなゴミの出し方をしてしまいます。
ゴミは、いわば「生活のうんち(排泄物)」。食べたもの(家の中に入れたもの)に応じて内容が変わるのも道理です。ゴミ出しのときに、ご近所さんと鉢合わせてしまうと、どこか気まずい気持ちになるのは、互いの排泄物など見たくもないし、見られたくもないからなのでしょう。
ゴミは種類を問わず、多くの場合収集日までは自宅(敷地)内に保管しておく必要があります。しかし「排泄物」の一種であるだけに、いかに臭い等含め自宅外に迷惑をかけないよう取り置くかということを主眼に、注意したいところです。古紙などは、臭いこそ出にくいものの、保管の仕方によっては放火されるような恐れもあるので、気をつけましょう。
●もえるゴミ
「もえる」とあるが、いわゆる「生ゴミ」の類もこのカテゴリ。いかに水分(水気)を残さないかが衛生上、また焼却処理にあたっての負担減という意味でも大切。水気のあるゴミはできるだけ水を切ること。DMなど、個人情報を記してある紙ゴミに包んで捨てると、互いの捨てにくさを打ち消し合える。
●粗大ゴミ
粗大ゴミは有料収集のことも多いが、材質よりも単純なサイズ感によって判定されがちなのでできるだけ小さく分解して捨てたい。ノコギリや万能ハサミなどを活用しよう。
●有害危険ゴミ
環境への悪影響が懸念されるゴミだけれども、ただ捨てるだけの立場からすると「これが有害だったなんて寝耳に水」ということも。収集に携わる方を危険にさらす恐れがあるので、くれぐれも間違った捨て方をしないようにしたい。代表的な有害危険ゴミに「乾電池、蛍光管、水銀体温計、ライター、スプレーかん・カートリッジ式ボンベ」などがある。
ゴミ収集の日数間隔や場所のしばり、分別の厳密さなど、多くは処理施設の能力など自治体の都合に左右されがちではあるのですが、個々の「捨てる」労力を減らす、もっとも効果的な方法は各家から出す「ゴミの総量を減らす」ということに尽きます。
とりもなおさず、それは家に「入れる」モノの選定によるものです。インターネットでの買い物、宅配につきものである発泡スチロール、ダンボールなどカサの張るもの、使い捨てのペットボトル、コンビニご飯のプラスティック容器等は、本来、つねに便利さと捨てる手間とをトレードオフしている点を自覚して選ぶべきなのでしょう。
外食や中食メインの食生活をいきなり自炊に変えても、「プラスティックゴミ」から今度は「生ゴミ」の発生や処理に手間取ることになる可能性があるなど、単純にゴミの多寡でライフスタイルを変化させれば解決する問題ではありません。
ただ、いつもどこかで「これは、どういったゴミに変化するだろう」という考えを持っているか持っていないかで、ゴミの内容や量は少しずつ変わってくるのではないでしょうか。















