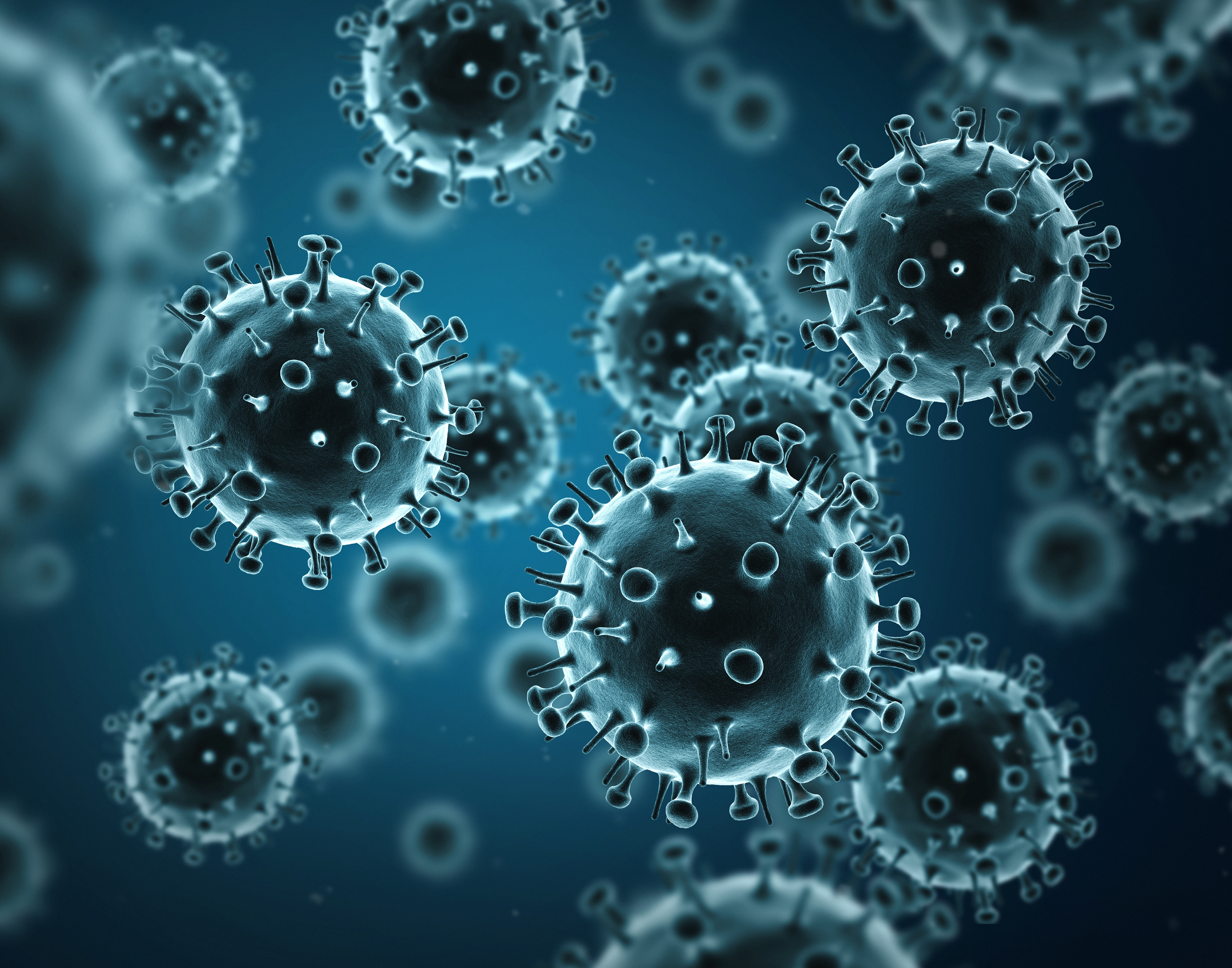2018.01.24 お家で出来る風邪・インフルエンザの感染予防と対策|ズバッと解決!<季節のお悩み相談室>

「ライノウイルス」、「コロナウイルス」、「RSウイルス」、「パラインフルエンザウイルス」、「アデノウイルス」などが、いわゆる「かぜ症候群」の原因となるウイルス。主に鼻腔から咽喉までの上気道に急性の炎症をもたらします。まれに「下気道」(気管、気管支、肺)まで炎症が及ぶこともあります。
ところでこの「ウイルス」は、カビや細菌のように「お風呂場の水っぽいところで勝手に殖えてしまう」といった類のものではありません。つまりダニアレルギー対策などのような、「掃除で予防」というアプローチをする疾患とは、ちょっと違います。
基本的に、人間のかかる「かぜ症候群」のウイルスは、「人間の身体の中」で殖え、かぜ症候群に罹っている人の「咳」や「クシャミ」によって飛び散った「飛沫」が、他の人の気道に入り込んで粘膜にくっつき、侵入して殖えてしまうというしくみで感染していきます。
ただしウイルスの侵入はあっても分かりやすく「発症」するかどうかは、周辺環境や罹った人の状況やさまざまな条件により、まちまちだったりします。
「インフルエンザ」も、ウイルス性の感染症なので、感染や発症のメカニズムは他の「かぜ症候群」と同じです。ただ、高熱(38度以上)が起こりやすく、頭痛、筋肉痛など全身の症状があらわれやすく、合併症(肺炎や脳炎)の懸念がある点には注意しなければいけません。
というわけで、よく「インフルエンザが怖いから」という理由で、ひとりでいても冬のあいだ中、住まいの中を湿気でいっぱいにしている人がいます。このように「加湿」が、風邪対策やインフルエンザ対策として有効だという認識でいる人は、そうではないという人に比べて、昨今、圧倒的に多数なのではないでしょうか?
でも、なぜ「加湿」がいいのでしょう?
まず冬場は屋外の空気が乾燥しがちですが、部屋の中の空気も暖房すればするだけ乾燥が促されてしまいます。
インフルエンザに罹った人がその部屋にいるとすると、咳やクシャミをしたときのそのウイルス入りの「飛沫」が、乾いた空気中では遠くまで飛んでしまいます。でも空気が湿ってさえいれば「飛ぶ」のが阻害されるため、感染予防としての「加湿」が推奨されるわけです。また加湿によって鼻や咽喉の粘膜の乾燥を防ぐという効果も期待されるようです。
もう一つ。「インフルエンザウイルス」は「寒冷乾燥」を好み「高温多湿」を嫌うという性質があります。高温多湿な環境では感染力が下がる、という研究結果も出ています。
ただしこの「高温多湿」を、目先の湿度計での湿度だけで判断したり、湿度だけをやみくもに上げればいいというわけではありません。部屋の空気1立方米あたりの水分量(乾燥指数、絶対湿度)が11〜17グラムであることを目安にすべき、という日本経済新聞による提言によれば、「気温20〜25度」「湿度50〜70%」を目安にし、「湿度40%」を下回らないように注意するというのが、インフルエンザなどのウイルスに感染した家族と過ごす部屋では、程よい数値であるようです。
口を開けて眠るような癖があり、喉の粘膜が乾きやすい人。乾燥した屋外、密室などで人ごみにいる時間が長い場合など、とりわけ鼻や咽喉に「他人のクシャミの飛沫」などが入りやすい場合には、「マスク」の着用で自衛したいところです。
うっかりウイルスが付着してしまった手で「鼻をほじる」、「素手で食べ物を食べる」行為なども、ウイルスが直に身体の中に入り込む契機となるため、石けんでの手洗い、帰宅後のうがいなども感染予防として大切な営みです。
また何より、「感染」してしまっても「発症」しにくい身体作りにも傾注したいところですね。バランス良い食事、しっかり取る睡眠。やみくもに感染を恐れるよりも、自分の足元を固めるほうに意識を向けることが、風邪、インフルエンザともに講じるべき対策の肝なのかもしれません。野菜の価格も高騰しがちな時期ではありますが、季節の青菜や根菜などからビタミンや食物繊維を摂っておきたいところです。